スポンサーリンク
今回は、
最近の話題のオンコロジー治療薬である、
「免疫チェックポイント阻害薬」(ICI)について、
記載させて頂きます。
免疫チェックポイント阻害薬は、
Immuno checkpoint inhibitor(ICI)もしくは、
Immuno oncology(IO)と略して記載されることがあり、
「免疫チェックポイント阻害薬」と記載すると文字数が長くなるため、
このブログでは、免疫チェックポイント阻害薬のことを略して「ICI」と
記載させて頂くこともありますので、ご了承ください。
まず、免疫チェックポイント阻害薬について
記載させて頂く前に、ご存知の方も多いかもしれませんが、
「がん」について、簡単に記載させて頂きます。
「がん」には大きく分けて、2種類あります。
「固形がん」と「血液がん」です。
「固形」がんには、大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、前立腺がん、腎がん、等があります。
「血液」がんには、悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫、等があります。
「固形がん」と「血液がん」の違いを、簡単に説明しますと、
「がん」ができる「場所」と「増殖の仕方」が、異なります。
固形がんは、「皮膚や臓器」にがん細胞が発生し、
血液がんは、造血幹細胞やリンパ球といった「造血器」にがん細胞が発生します。
また、増殖の仕方ですが、
固形がんは、組織に癒着して、腫瘍と呼ばれる塊を作りますが、
血液がんは、基本的には組織に接することなく、
1個1個の細胞が同時多発的に増殖をくり返します。
そのため、血液がん治療薬は、1個1個のがん細胞を標的にするため、
固形がんと比べ、薬物治療が奏功しやすい(抗がん剤が効きやすい)、と言われています。
一方、固形がんは、腫瘍のかたまりを作るため、
奥にあるがん細胞まで抗がん剤が届かず、効果が限定的な場合もあるため、
効きずらいこともある、と言われています。
「がん」は大きく上記の2つに分類されるのですが、
さらに細かく見ますと、固形がんは、固形がんの中でも2つに分けられます。
【固形がん】
①上皮細胞がん(大腸がん、肺がん、乳がん等)
②非上皮細胞がん(骨や筋肉などの非上皮から発生するがん、いわゆる肉腫です)
この②の非上皮細胞に発生するがんは、肉腫(sarcoma、サルコーマ)と呼ばれており、
骨や筋肉などの非上皮性細胞から発生するがんのことで、
代表的な肉腫には、骨肉腫、軟骨肉腫、横紋筋肉腫、平滑筋肉腫、線維肉腫、脂肪肉腫、血管肉腫等が
あります。
この非上皮がんである「肉腫」は、「骨や筋肉」に存在する「がん」のため(いわゆる臓器の奥に存在)、
抗がん剤が、上皮にできる固形がんよりも、効きにくいと、言われています。
「がん」の分類についてまとめます。
【がんの分類】
①固形がん(=上皮がん=がん腫、ex 大腸がん、肺がん、乳がん、etc)
②固形がん(=非上皮がん=肉腫、サルコーマ)
③血液がん(=造血組織がん、ex 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、etc)
次に、「がん」の治療について、
簡単に記載させて頂きます。
「がん」には大きくわけて、
「固形がん」と「血液がん」があり、
抗がん剤は、血液がんの方が効きやすい、ということも上記に簡単な理由とともに、
記載させて頂きました。
固形がんと血液がんに使用される抗がん剤は、異なることがほとんどですが、
免疫チェックポイント阻害薬は、なんと固形がんにも血液がんに使用できるのです。
もちろんすべての固形がん、血液がんに使用できるわけではないでし、
免疫チェックポイント阻害薬を使用しても有効性が期待しにくい、固形がん、血液がんも
存在します。
さて、ここで話を「がん」の治療に戻しますが、
「がん」治療の目的は、3つあります。
【がん治療の目的】
①「がん」からの治癒(根治)
② 延命(生存率の向上)
③ 緩和(ケア)
固形がん、血液がんに関わらず、
「がん細胞」をすべてやっつけ、体内から排除し、
「がん細胞」からの根治(治癒)ができればベストなわけですが、
実際には、難しい場合も多く、
特に、固形がんでは、抗がん剤治療を開始する場合の多くは、
「延命」や「緩和ケア」といった目的になることが多いのが現状です。
一方、血液がんに関しては、ここ数年~数十年間の医薬品開発の進歩は凄まじく、
不治の病といわれていた白血病が薬を飲み続けていれば、
症状やがん細胞の増殖を抑えられ、
治癒が目指せるかもしれない治療にまで発展しています。
したがって、一部の白血病や多発性骨髄腫といった血液がんは、
薬で何とか治療が可能なところにまで来ています。
一方、固形がんの多くは、薬で治癒(根治)は難しく、
固形がんに対する薬物治療の目的の多くは、
数カ月~数年間の延命(生存率向上)、が多いのが現状です。
固形がんの治療の基本は、手術であり、
手術で腫瘍が取り切れれば、根治が可能な場合も多いのです。
ただし、「がん」が原発巣から他臓器に転移していると、生存率が下がることが多く、
原発巣から転移しないうちに、手術し、取り切ることが必要です。
しかし、原発巣(腫瘍が発生した部位)を手術で切除したとしても、
他臓器への転移や再発が認められた場合は、再度手術する場合もありますが、
全身に作用する抗がん剤治療が開始されることが多いです。
ただし、そこで抗がん剤治療を開始したとしても、
完全にがん細胞をやっつけることは難しく(理由として、他臓器や全身へ転移していることも多いため)、
延命目的の抗がん剤治療になるケースが多いのです。
がん細胞に標的を当てた、発売当時は画期的と言われていた「分子標的薬」を使用したとしても、
数か月~数年の延命が期待できるものの、固形がんに関しては、治癒は難しい状況でした。
ところが、免疫チェックポイント阻害薬は、
もしかしたら、固形がんであっても、「がん」からの治癒(根治)が期待できる
かもしれない薬剤なのです。
ここ数年、オンコロジー治療の選択肢が増え、
「オプジーボ」や「キイトルーダ」といった抗PD-1抗体である、
免疫チェックポイント阻害薬(ICI)が発売されました。
ICIの一番のメリットは、
「がん」からの治癒(根治)が期待できる点だ、とも言われています。
免疫チェックポイント阻害薬は自己の免疫機能を高め、
「がん」細胞を自らの免疫機能にて、やっつける薬剤です。
一度高めた免疫は持続する傾向があり、免疫チェックポイント阻害薬による、
効果の持続性が示唆されています。
そのため、免疫機能が持続し、がん細胞に働き続け、
「がん」からの治癒(根治)が期待できるのではないか、と言われています。
(作用機序やデータの詳細はこの記事の途中で詳しく紹介します。)
ただし、このICIは、すべてのがん患者さんに効果があるかと言われれば、
そのようなことはなく、効果がある方は、
免疫チェックポイント阻害薬が効きやすいがんの、
2割ほどではないか、と言われています。
この2割が多いか少ないかは、意見のわかれるところかもしれませんが、
今までの治療の選択肢や可能性が増えたことは、望ましいことかと思われます。
免疫チェックポイント阻害薬には、「がん」の種類によって、
効きやすい「がん」と効きにくい「がん」があることがわかっています。
【免疫チェックポイント阻害薬が効きやすいがん】
・メラノーマ(悪性黒色腫、皮膚がんの一種)、肺がん、腎がん、etc
【免疫チェックポイント阻害薬が効きにくいがん】
・前立腺がん、膵臓がん、大腸がん(一部の大腸がんを除く)、etc
すなわち、メラノーマや肺がんでは、
免疫チェックポイント阻害薬を使用すると、約2割の患者さんで効果がある、
ということです。
では、なぜ、「がん」の種類によって、
免疫チェックポイント阻害薬の有効性に差があるのでしょうか?
明確な医学的根拠のあるエビデンスはまだ出ていませんが、
可能性として強く言われていることは、
免疫チェックポイント阻害薬は、遺伝子変異のある「がん」に効きやすい
可能性が高い、ということです。
免疫チェックポイント阻害薬の作用機序は、
T細胞の機能を活性化させて、T細胞が「がん細胞」をやっつけるようにさせる、
薬剤です。
免疫チェックポイント阻害薬が直接、がん細胞に作用するわけではなく、
あくまで自己免疫機能を高め、がん細胞をやっつける薬剤です。
「がん細胞」というのは、遺伝子が変異してがん細胞になるわけですから、
遺伝子変異のある細胞です。
これが多いほど(遺伝子変異のある細胞が多いほど)、
免疫チェックポイント阻害薬が機能しやすくなる(T細胞が非自己を認識し攻撃しやすくなる)ため、
遺伝子変異の多いがんは、免疫チェックポイント阻害薬が効きやすいと言われています。
したがって、メラノーマや肺がんが免疫チェックポイント阻害薬が効きやすい理由として、
メラノーマや肺がんは、遺伝子変異の多いがんである、
という可能性が示唆されています。
一方、膵臓がんや前立腺がんは、がんそのものに、遺伝子変異が(メラノーマや肺がんに比べ)、
少ないため、免疫チェックポイント阻害薬が効きにくい、と言われています。
抗PD-1抗体である「オプジーボ」(ニボルマブ)の最初の適応が
皮膚がんの一種である「メラノーマ」だった理由の1つに、
「メラノーマ」がすでに、免疫チェックポイント阻害薬が効きやすい、ということが
わかっていたから、とも言われています。
もちろんメラノーマに有効な治療薬が少なかったから、
という理由もあるかもしれません。
最近は、肺がん治療で免疫チェックポイント阻害薬が使用される機会が多くなり、
ASCOやESMOといった、海外での腫瘍学会でも、肺がん治療における免疫チェックポイント阻害薬の
使用データ等の発表が多くされていますが、肺がん治療における免疫チェックポイント阻害薬の貢献度が
比較的高いため、肺がんからの発表が多くなっています。
もちろんそれ以外の適応でも続々と治験や臨床試験が実施されており、
さらなる適応拡大が期待されている薬剤です。
ということで、
免疫チェックポイント阻害薬は効きやすい「がん」があり、
効きやすい「がん」では、今後の臨床試験次第ではありますが、
治癒(根治)が期待できるかもしれない薬剤である、ということです。
また、上記にも少し記載しましたが、
免疫チェックポイント阻害薬は、作用機序としても、画期的です。
今までの抗がん剤は、主に2種類に分けられており、
昔は、ケモ(化学療法)と呼ばれる細胞障害性抗がん剤(パクリタキセル、シスプラチン等)しかなく、
その後、がん細胞を狙い撃ちした分子標的薬が登場しました。
スポンサーリンク
分子標的薬は、がん細胞を狙い撃ちした薬剤ですが、がん細胞に狙い撃ちしているため、
正常細胞には作用しないかと言えば、そんなことはなく、分子標的薬であっても、
副作用の発現頻度が高い薬剤は多くあります。重篤な副作用発現の可能性もある分子標的薬も多く、
決して副作用の少ない薬剤ではありません。もちろん比較的副作用の出にくい薬剤も一部ありますが、
分子標的薬といえども、副作用マネジメントは欠かせません。
抗がん剤治療は、病院に来て治療を受けるイメージがあるかもしれませんが、
化学療法の薬剤や免疫チェックポイント阻害薬は点滴静注がほとんどのため、
入院や外来通院にて、病院のケモ室(化学療法治療室)等で
治療を受けることがほとんどです。
一方、分子標的薬は経口剤がほとんどのため、ケモ室での投与はあまりなく、
外来で薬をもらって、ご自宅で内服することがほとんどです。
ただし、導入時は、病院で入院して導入開始するケースもあります。
ということで抗がん剤の3種類を下記にまとめます。
【抗がん剤の種類】
①細胞障害性抗がん剤=殺細胞性抗がん剤=化学療法(パクリタキセル、シスプラチン、等)・・・点滴
②分子標的薬(イレッサ、グリベック、等)・・・経口投与
③免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ、キイトルーダ、等)・・・点滴投与
話を免疫チェックポイント阻害薬の作用機序に戻します。
免疫チェックポイント阻害薬が今までの抗がん剤と一線を画すのは、
今までの抗がん剤が直接がん細胞に作用する薬剤だったのに対し、
免疫チェックポイント阻害薬は、
免疫機能を高め、がん細胞をやっつけるという、
間接的にがん細胞に作用する薬剤です。
体内には、T細胞というがん細胞を非自己と認識して、
がん細胞をやっける細胞が存在します。
しかし、がん細胞はT細胞にやっつけられないために
必死に抵抗します。
がん細胞は、T細胞の働きを抑制させる、
ブレーキ機能を発動させます。
そのブレーキ機能がPD-L1といいます。
PD-L1を発動させることで、T細胞の機能を抑制しようとします。
では、どうやって、T細胞の働きを抑制させるのかというと、
がん細胞側にあるブレーキ機能のPD-L1と、T細胞側にあるPD-1を結合させることで、
T細胞の働きを抑制させるのです。
このままでは、がん細胞にT細胞の機能(がん細胞をやっつける機能)が抑えられてしまいます。
ここで登場するのが、免疫チェックポイント阻害薬です。
免疫チェックポイント阻害薬は、
T細胞側のPD-1と結合することにより、
がん細胞のPD-L1とT細胞の結合することを防ぎます。
これが免疫チェックポイント阻害薬です。
「オプジーボ」(ニボルマブ)や「キイトルーダ」(ペムブロリズマブ)は、
T細胞側のPD-1と結合し、
「テセントリク」(アテゾリズマブ)や「イミフィンジ」(デュルバルマブ)は、
がん細胞側のPD-L1と結合することで、
T細胞の機能を活性化させ、がん細胞をやっつけます。
したがって、
免疫チェックポイント阻害薬は、人体の免疫機能を高めるため、
効果が持続するのではないか、と言われています。
それゆえに、免疫チェックポイント阻害薬は、治癒(根治)が期待できるのではないか、
と言われています。
実際の臨床試験データでも、
「オプジーボ」のデータを見てみますと、2017年4月、AACR(米国がん学会年次総会)から、
興味深い発表がありました。
タイトルは、2017年4月3日にAACRから発表された、
「Five-year Survival Rate For Nivolumab-treated Advanced Lung Cancer Patients Much Higher Than Historical Rate」(The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins Julie Brahmerより)です。
記事内容の詳細は省きますが、
転移性非小細胞肺がん(NSCLC)の患者さんを対象にニボルマブを投与し、
5年生存率が16%に達した、という報告でした。
転移性非小細胞肺がんにおける、今までの5年生存率は、わずか4%ほどだったのに対し、
今回、ニボルマブ(オプジーボ)を投与した5年生存率は、なんと4倍の16%だったという報告でした。
また、この報告は、治療歴を有する進行期非小細胞肺がん患者(129例)を対象にオプジーボを評価した第1相用量漸増臨床試験である「CA209-003試験」の5年生存率のデータに基づいた試験です
この試験の年次ごとの生存率は、
1年生存率42%、2年生存率24%、3年生存率18%および5年生存率16%でした。
したがって、3年生存率と5年生存率は大きく変わらなかった報告であり、
これはすなわち、可能性として、「がん」からの治癒が期待できる可能性を示唆しています。
他の試験での「オプジーボ」の生存率の曲線を見ても、年次を追うごとに平行に近づいているケースが見られます。今での抗がん剤では、ほぼ完全に曲線が下に下がってしまうケースがほとんどでした。
作用機序と臨床試験の5年生存率や生存曲線からも、
もしかしたら、「オプジーボ」等の免疫チェックポイント阻害薬は、
「がん」からの治癒(根治)が期待できるかもしれない、希望のある薬剤なのかもしれません。
今までの抗がん剤は、血液がんや一部の固形がんを除き、
ほとんど延命が主目的であり、治癒は期待しにくい現状がありました。
免疫チェックポイント阻害薬はまだ発売して数年という状況であり、
今後のエビデンス次第ではありますが、がん患者さん希望をもたらすことの
できる薬剤なのかもしれません。
では、免疫チェックポイント阻害薬はメリット(有効性)だけかというと、
そんなはずはなく、デメリット(副作用)も存在します。
ICIは、免疫機能を高めるため、
免疫系の副作用が発現することがあります。
ICIは、効果が持続することや
遅れて効果が発現することがあります。
したがって、一度高めた免疫機能はそのままの状態になることもあり、
それが効果面ではメリットになるものの、副作用面ではかなりのデメリットにすら
なりえます。
具体的には、過剰な免疫機能が自己免疫系疾患を引き起こすことがあります。
それが全身性の免疫疾患を引き起こすことさえありえます。
例えば、自己免疫疾患である、1型糖尿病を引き起こすことがあり、
1型糖尿病は、薬物治療で改善することができず、1型糖尿病になった場合は、
一生インスリンを服用(注射)することになります。
一生インスリンを服用する可能性と、治療効果を最大限考慮しながら、
免疫チェックポイント阻害薬を使用考える必要があるのです。
それ以外にも、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、甲状腺機能低下症、etc
といった副作用が発現することがあります。
今までの抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬の副作用を比べると、
今までの抗がん剤は、服用を中止すれば、副作用が治まり、改善する傾向(可逆的傾向)があったものの、
免疫チェックポイント阻害薬は、服用を中止しても、副作用が治まらない、(不可逆的)副作用が
は発現するケースがあり、注意が必要です。
特に、1型糖尿病等の自己免疫疾患は、不可逆的な副作用であり、
一度1型糖尿病になってしまうと、インスリンを服用し続ける必要があります。
免疫チェックポイント阻害薬は、
今までの抗がん剤と比べ、比較的副作用が少ない、といれることも多いですが、
発現した副作用は重篤な副作用になるケースもいくつかあり、
使用する際は、臨床検査値だけでなく、患者さんからの訴えによる、
細かなら体調変化のチェックも欠かせないため、より副作用マネジメントがより重要な薬剤とも言えます。
ただし、副作用の頻度そのものは、言われている通り、
既存の抗がん剤に比べ、少ない傾向はありますので、
上手く使用し、有効性の恩恵を最大限に受けたい薬剤ではあります。
さて、最近の免疫チェックポイント阻害薬のトレンドは併用療法が多く、
もちろん、ICIとICIの併用もすでにありますが(オプジーボ&ヤーボイ等)、
免疫チェックポイント阻害薬と化学療法を併用する臨床試験も多く実施されています。
2018年6月に開催されたASCO(米国腫瘍学会)でも、
この話題はいくつかあり、非小細胞肺がんの1st lineは、
今後、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用が1stになるかもしれません。
それだけ併用療法で、良い結果が出ています。
もちろん免疫チェックポイント阻害薬の単剤でも、
一定の有効性が認められていますが、
他剤と併用すると、より効果が良いという報告がいくつかあり、
今後は併用が主流になるかもしれません。
免疫チェックポイント阻害薬は、
化学療法(細胞障害性抗がん剤、いわゆる従来の抗がん剤、exシスプラチン等)と併用することで、
より免疫機能が高まり、T細胞の働きが活性化することが知られています。
化学療法の抗がん剤は、細胞毒性があるため、
遺伝子変異を引き起こしやすいという報告があり、
遺伝子変異を引き起こしやすい「がん」は、
免疫チェックポイント阻害薬が効果的である、
可能性が示唆されていめ、相乗効果があるかもしれない、と言われています。
化学療法の抗がん剤の中には、Tregといった抑制性T細胞を減少させるため、
よりT細胞の機能を高める可能性が示唆されている薬剤も存在します。
免疫チェックポイント阻害薬は、より遺伝子変異のある「がん」の方が、
T細胞が非自己と認識しやすいため、遺伝子変異の多い「がん」の方が、
T細胞が活性化し、効果が高まると言われています。
ということで、
免疫チェックポイント阻害薬と化学療法は現時点では、
併用した方が効果が良いのではないかという流れになっています。
もちろん明確なエビデンスが確立しているわけではないため、
今後の研究次第ではありますが、現時点では、併用した方がより効果が期待できるのかもしれません。
以上、
オンコロジー治療の現在のトレンドである、
免疫チェックポイント阻害薬について、記載してみました。
「がん」治療の基本は、多くの先生方がおっしゃっていることですが、
「早期発見」、「早期治療」が原則です。
血液がんは薬剤で生存率が大幅に伸びましたが、
固形がんは、手術で取り切れなかった腫瘍や転移した腫瘍に対する抗がん剤治療では、
生存率が数か月~数年という状況です。
固形がんの病期はステージⅠ~Ⅳの主に4つにわけられますが、
Ⅳに近づくほど、重症になり、治療が手遅れになるケースもあります。
しかし、早期に発見し、ステージⅠ、Ⅱといった早い段階で手術等の治療をすることで、
「がん」を完治することも可能です。
免疫チェックポイント阻害薬という、治癒が期待できるかもしれない、がん免疫療法がありますが、
この免疫チェックポイント阻害薬が効く患者さんは限られています。
医学薬学は日々進歩していきますが、
それでも治療が難しいケースは多く存在しています。
薬物治療で、生存率の向上や「がん」からの治癒(根治)が
期待できるかもしれない免疫チェックポイント阻害薬に大いに期待したいですね。
今後、良い臨床報告を期待したいです。
スポンサーリンク
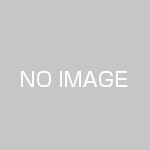
この記事へのコメントはありません。